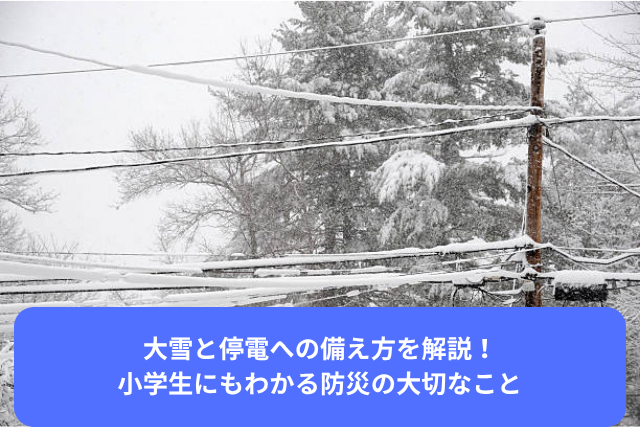この記事では、大雪による停電に備えて、家庭でできる準備や役立つ防災アイテムをわかりやすく解説します。
冬の停電は、暖房や照明が使えなくなり、寒さや暗闇で不安を感じる方も多いでしょう。
結論から言うと、事前に食料・水・暖房・電源をしっかり準備しておくことで、停電中でも安全に過ごすことができます。
特に、スマホや照明を動かせるポータブル電源があると、安心感が大きく違います。家族で防災ルールを決めておくことも大切です。
もっと詳しく知りたい方はこのまま読み進めて、すぐに準備を始めたい方はJackery(ジャクリ)公式サイトをチェックしてみてください。
![]()
大雪による停電はなぜ起こるのか?
大雪による停電は、冬の寒冷地だけでなく都市部でも起こり得る深刻なトラブルです。
ここでは、雪が電線や設備に与える影響と、なぜ停電が発生するのかをわかりやすく解説します。
雪で電線が切れる・ショートする仕組み
大雪が降ると、雪が電線や鉄塔に付着して「着雪」と呼ばれる現象が起こります。
特に水分を多く含んだ重い雪(ぼたん雪)は、電線に大きな負荷をかけ、最悪の場合は断線を引き起こします。
また、風で電線が揺れた際に、着雪した電線同士が接触してショート(短絡)することもあります。
これを「スリートジャンプ現象」と呼び、雪国では頻繁に発生する停電原因のひとつです。
電力会社ではこうしたトラブルを最小限に抑えるために、電線を自動遮断するシステムを導入していますが、完全に防ぐことは難しいのが現状です。
雪国だけじゃない!都市部でも起こる停電リスク
意外かもしれませんが、雪があまり降らない地域でも停電は発生します。
理由は、温暖な地域ほど降る雪が湿って重く、電線や樹木への負担が大きいためです。
たとえば、2022年の新潟県の大雪では、雪の重みで木が倒れ、電線が切断されて約7万戸が停電しました。
都市部では設備が地中化されている場所もありますが、郊外や住宅街では依然として架空電線が多く、「雪が少ない地域=安全」とは限りません。
大雪で停電が起きたときに困ること
大雪で停電が発生すると、ただ「電気が止まる」だけでは済みません。
暖房や照明、通信、そして水道までもが影響を受け、生活全体がマヒしてしまいます。
ここでは、停電時にどのようなトラブルが起こるのかを具体的に見ていきましょう。
暖房や照明が使えないことで起きる危険
冬の停電で最も深刻なのが、暖房が使えなくなることです。
エアコンや電気ストーブ、床暖房などはすべて電力で動くため、停電時には機能を停止します。
暖房が使えないと、室内の温度は数時間で10℃以上低下し、低体温症の危険が高まります。
特に高齢者や乳幼児は体温調節が苦手なため、命に関わるケースも少なくありません。
照明が使えない夜間も危険です。
暗闇では転倒事故や火の取り扱いミスが増え、二次災害を引き起こすことがあります。
そのため、LEDランタンや乾電池式ライトを複数準備しておくことが重要です。
できれば、1部屋に1つを目安に常備しておくと安心です。
水・食料・通信が止まることでの生活への影響
停電は、電気以外のライフラインにも影響を与えます。
特にマンションでは、電動ポンプが止まることで水道が使えなくなる場合があります。
トイレが流せなくなり、衛生環境が悪化することも。
また、冷蔵庫も停止するため、約6時間で食材が傷み始めると言われています。
通信面でも、停電が長引くとWi-Fiルーターや携帯基地局が停止し、スマートフォンが使えなくなる可能性があります。
このような事態に備えて、モバイルバッテリーやポータブル電源を常備し、情報収集手段を確保しておきましょう。
特に防災情報や避難指示はスマホから入手することが多いため、電源の確保は命を守る要素といえます。
大雪の停電に備えておくべき防災グッズ
大雪による停電に備えるためには、「命を守る基本セット」+「冬の防寒対策」+「電力の確保」の3つを意識して準備することが大切です。
ここでは、家庭で揃えておきたい防災グッズの基本を解説します。
家族を守る基本の防災セット(食料・飲料水など)
まず最低限必要なのが、食料と飲料水の備蓄です。
政府や自治体では、1人あたり3日分(理想は7日分)の備蓄を推奨しています。
水は1日あたり3リットル/1人を目安に確保しましょう。
飲料だけでなく、調理や手洗いにも使うため、多めの準備が安心です。
非常食は、常温保存ができるレトルト食品・缶詰・乾パン・アルファ米などを選びます。
食べ慣れた味を選ぶことで、子どもや高齢者も安心して食べられます。
また、ガスボンベ・カセットコンロを用意しておくと、温かい食事を作れるので体温維持にも効果的です。
寒さ対策に欠かせない暖房器具と代替手段
停電時の最大の課題は「寒さ」です。
電気が止まるとエアコンや電気ヒーターは使えなくなるため、電気を使わない暖房器具を準備しておきましょう。
おすすめは以下の3種類です:
-
石油ストーブ:燃料さえあれば電気不要で暖が取れる
-
カセットガスストーブ:手軽でコンパクト、短時間使用に最適
-
湯たんぽ・使い捨てカイロ:電気がなくても体を温められる
ただし、火を使う器具は換気を忘れずに行いましょう。
また、ストーブの燃料(灯油・ガス)は最低でも2〜3日分を備蓄しておくと安心です。
停電時に役立つ“電力を確保する方法”の基本(電池・発電・簡易電源)
停電が長引くと、照明・通信・調理すべてに電力が必要になります。
そのため、家庭でも電力を一時的に確保できる手段を準備しておくことが重要です。
主な電力確保の方法は以下の通りです:
-
乾電池式ライト・ラジオ:単3・単4電池を多めにストック
-
手回し充電式ライト:電池がなくても発電できる
-
モバイルバッテリー:スマホや小型家電の充電用
-
簡易的なポータブル電源:照明・小型ヒーターなどに利用可能
これらの基本装備を整えておくことで、停電時の不安を大幅に軽減できます。
次章では、より実用的で長時間使えるポータブル電源の必要性とおすすめモデルについて詳しく紹介します。
停電時のポータブル電源の必要性とおすすめモデル紹介
停電が長引くと、照明・通信・暖房・調理などあらゆる生活機能が止まってしまいます。
そんなときに強い味方となるのが、ポータブル電源です。
ここでは、停電時にポータブル電源が必要な理由と、選び方・おすすめモデルを紹介します。
なぜ停電時にポータブル電源が重要なのか
停電が数時間で復旧する場合もありますが、大雪による停電は最長で数日間続くこともあります。
特に寒冷地では、雪の重みで電線が損傷し、復旧作業が遅れるケースが多いです。
その間、スマートフォンや暖房器具が使えないと、
-
家族との連絡手段の喪失
-
室温の低下による低体温症の危険
-
情報が入らないことによる避難遅れ
といったリスクが生じます。
ポータブル電源があれば、スマホやパソコンはもちろん、電気毛布・小型ヒーター・ケトル・照明なども動かすことができます。
まさに、停電時の“命を守る電力”を確保するための必需品といえるでしょう。
容量・出力・安全性で選ぶポータブル電源のポイント
ポータブル電源を選ぶ際は、以下の3つのポイントを確認しましょう。
-
容量(Wh):どれくらいの電力を蓄えられるか
→ スマホ充電だけなら500Wh前後、照明や小型家電も使うなら1000Wh以上が目安。 -
出力(W):どんな機器が動かせるか
→ 電気ケトルやドライヤーなどを使うなら1000W以上が必要です。 -
安全性・信頼性:長期保存や冬場の使用に耐えられるか
→ PSE認証済みや過充電防止機能付きモデルを選ぶと安心。
また、太陽光パネルと組み合わせれば、停電中でもソーラー充電で電力を再補給できるため、長期停電にも対応できます。
Jackery(ジャクリ)の人気モデルと特徴比較
| モデル名 | 容量(Wh) | 定格出力(W) | フル充電時間(AC充電) | おすすめ世帯 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jackery 500 New | 約512Wh | 500W | 約2時間半 | 1~2人暮らし | 軽量で持ち運びやすく、スマホ・照明・ノートPCに最適。短時間の停電にも対応。 |
| Jackery 1000 Plus | 約1,264Wh | 2,000W | 約1.7時間 | 2~4人家族 | 家庭用家電にも対応。電気毛布・炊飯器・テレビの使用が可能。防災・アウトドア両対応。 |
| Jackery 2000 Plus | 約2,048Wh | 3,000W | 約2時間 | 4人以上の大家族 | 冷蔵庫・電子レンジ・ヒーターなど長時間運転可能。長期停電にも安心の大容量モデル。 |
すべてのモデルがソーラーパネル充電対応で、停電中でも再充電が可能です。
特にJackery 1000 Plusは、家庭の非常用電源としてバランスが良く、
初めてのポータブル電源導入にも最適なモデルです。
子どもと一緒に学ぶ!小学生にもできる大雪対策
大雪による停電は、子どもにとっても不安な出来事です。
ですが、事前に「どう行動すればいいか」を家族で共有しておけば、落ち着いて安全に過ごすことができます。
ここでは、小学生でも理解できる大雪対策のポイントを紹介します。
停電になったときに落ち着いて行動する方法
停電が起きると、家の中が一気に暗くなります。
そのときに大切なのは、慌てずに行動することです。
子どもに伝えておきたい基本行動は次の3つです:
-
まずは家族を呼ぶ – 無理に動かず、親や大人のいる場所へ行く。
-
明かりを確保する – 懐中電灯やLEDランタンの場所を覚えておく。
-
安全を確認する – 割れたガラスや倒れた家具に近づかない。
夜間の停電では、転倒やケガが起きやすいため、子どもの手が届く場所に懐中電灯を常備しておくと安心です。
また、あらかじめ家族全員で停電時の行動を練習しておくことも効果的です。
家族で決めておきたい避難・連絡ルール
大雪や停電時に最も大切なのは、家族の安否をすぐに確認できることです。
災害時は通信が混雑するため、あらかじめ家族間の連絡ルールを決めておきましょう。
おすすめは以下の方法です:
-
連絡先を紙に書いて冷蔵庫や玄関に貼る
-
安否確認用のLINEグループを作る
-
連絡が取れないときの集合場所(例:近くの学校や公民館)を決めておく
また、小学生の子どもでも「どこに避難すればいいのか」「非常袋はどこにあるのか」を理解しておくことで、いざという時に慌てず行動できます。
学校でできる防災行動と日常の練習ポイント
学校でも大雪や停電が起きることがあります。
その際に先生の指示に従えるよう、普段から防災意識を持たせることが大切です。
子どもと一緒に確認しておきたいポイントは次の通りです:
-
学校に防寒具やブランケットを1枚常備する
-
教室の避難経路を把握しておく
-
防災訓練では「なぜその行動を取るのか」を家庭で話し合う
また、家庭でも「今日はもし停電したらどうする?」と会話形式で練習しておくと、子どもが自分の役割を理解しやすくなります。
楽しみながら防災意識を育てることが、最も効果的な教育です。
大雪に備えるための家庭のチェックリスト
大雪による停電は「いつか起きるかもしれない」ではなく、「毎年どこかで起きている」現実的な災害です。
日常の中で備えを習慣化しておくことで、いざという時に慌てずに行動できます。
ここでは、家庭でできるチェック項目をまとめました。
停電前に確認すべき家の設備と準備
停電に備えておくべき家庭設備の確認ポイントは次の通りです:
-
懐中電灯・ランタンの電池は入っているか
-
スマホのモバイルバッテリーは常に満充電か
-
**暖房器具(石油ストーブ・ガスストーブ)**は燃料を備蓄しているか
-
冷蔵庫・冷凍庫の保冷対策はできているか
-
非常用トイレや簡易バケツを常備しているか
-
断水時のために浴槽へ水を貯める習慣があるか
また、家のブレーカーやガス元栓の位置を家族全員が把握しておくと、停電時の安全確認がスムーズに行えます。
電源復旧後に家電を一斉に使うとブレーカーが落ちることもあるため、復旧時は1つずつ電源を入れるのがポイントです。
日常からできる防災意識の育て方
防災は「特別な準備」ではなく、日常生活の中で自然に取り入れることが大切です。
次のような習慣を意識すると、家族全員の防災力が高まります。
-
“ローリングストック法”で食料・水を常に新しい状態に保つ
-
使い終わったらすぐ補充する仕組みを作る
-
季節の変わり目に家族で防災チェックデーを実施する
-
子どもにも「なぜ防災が大切なのか」を話して共有する
これらを習慣化することで、「備え」が特別な行動ではなく、生活の一部になります。
とくに冬の時期は、燃料・バッテリー・カイロなど消耗品の確認をこまめに行うことが大切です。
大雪と停電の備えは「家族全員の意識」から始まる
大雪による停電は、どの地域でも起こり得る身近なリスクです。
しかし、正しい知識と日ごろの備えがあれば、寒さや暗闇の中でも安心して過ごすことができます。
家庭での防災対策は、「自分を守る」だけでなく「家族を守る」ための行動です。
食料・水・電源を確保し、暖房や照明の代替手段を用意しておくことで、長期停電にも対応できます。
また、子どもにもわかりやすく説明し、「家族みんなで防災を意識する」ことが最も大切です。
もしまだ準備ができていない場合は、この記事を参考に、今日から少しずつ始めてみましょう。
停電時に頼れるポータブル電源として、Jackery(ジャクリ)シリーズもぜひチェックしてみてください。
災害は予告なく訪れます。だからこそ、今の備えが未来の安心につながります。
大雪による停電への備えに関するよくある質問
Q1:大雪で停電が起こる主な原因は何ですか?
A1:主な原因は、雪の重みで電線が切れたり、湿った雪が電線に付着してショート(短絡)することです。特に風を伴う雪では「ギャロッピング現象」が発生し、電線同士が接触して停電を引き起こすことがあります。
Q2:停電時、エアコンや電気ストーブが使えないときはどうすればいいですか?
A2:電気を使わない石油ストーブやカセットガスストーブを準備しましょう。燃料は最低でも2〜3日分備蓄し、換気を忘れずに使用することが重要です。併せて湯たんぽやカイロも活用すると安心です。
Q3:家庭でどのくらいの非常食と水を備蓄すればよいですか?
A3:最低限の目安は1人あたり3日分、可能であれば7日分を推奨します。水は1日3リットル/1人を基準に確保しましょう。非常食は缶詰やレトルト食品、アルファ米などの常温保存できるものが便利です。
Q4:停電時に役立つポータブル電源は、どのように選べばよいですか?
A4:選ぶポイントは容量(Wh)・出力(W)・安全性の3つです。
スマホ充電程度なら500Wh前後、照明や小型家電も使うなら1000Wh以上が目安。
防災用途ならPSE認証付き・過充電防止機能のあるモデルを選ぶと安心です。
Q5:小学生の子どもにもできる停電対策はありますか?
A5:はい。停電時に懐中電灯の場所を覚えること、家族を呼ぶこと、危ない場所に近づかないことを伝えておきましょう。
また、家族で「停電ごっこ」をして行動を練習しておくと、実際の災害時にも落ち着いて行動できます。
Q6:ポータブル電源のおすすめメーカーはありますか?
A6:信頼性と防災実績の点では、Jackery(ジャクリ)がおすすめです。
家庭用からアウトドア用まで幅広いラインナップがあり、Jackery 1000 Plusは家族4人の停電対策にも十分な容量を備えています。
大雪と停電への備え方を解説!小学生にもわかる防災の大切なこと まとめ
大雪による停電への備えについて解説をしてきました。
停電はいつ起きてもおかしくない身近なリスクですが、日ごろの準備で被害を最小限に抑えることができます。
食料や水の備蓄に加えて、電気を確保する手段を持っておくことで、冬の寒さや暗闇の不安を大きく減らせます。
中でも、スマホや暖房器具を動かせるポータブル電源は、家族の安全を守る心強い味方です。
まだ準備をしていない方は、今から少しずつ始めましょう。
Jackery(ジャクリ)公式サイトでは、停電対策にぴったりのモデルが詳しく紹介されています。
今すぐチェックして、安心できる冬の備えを整えてください。